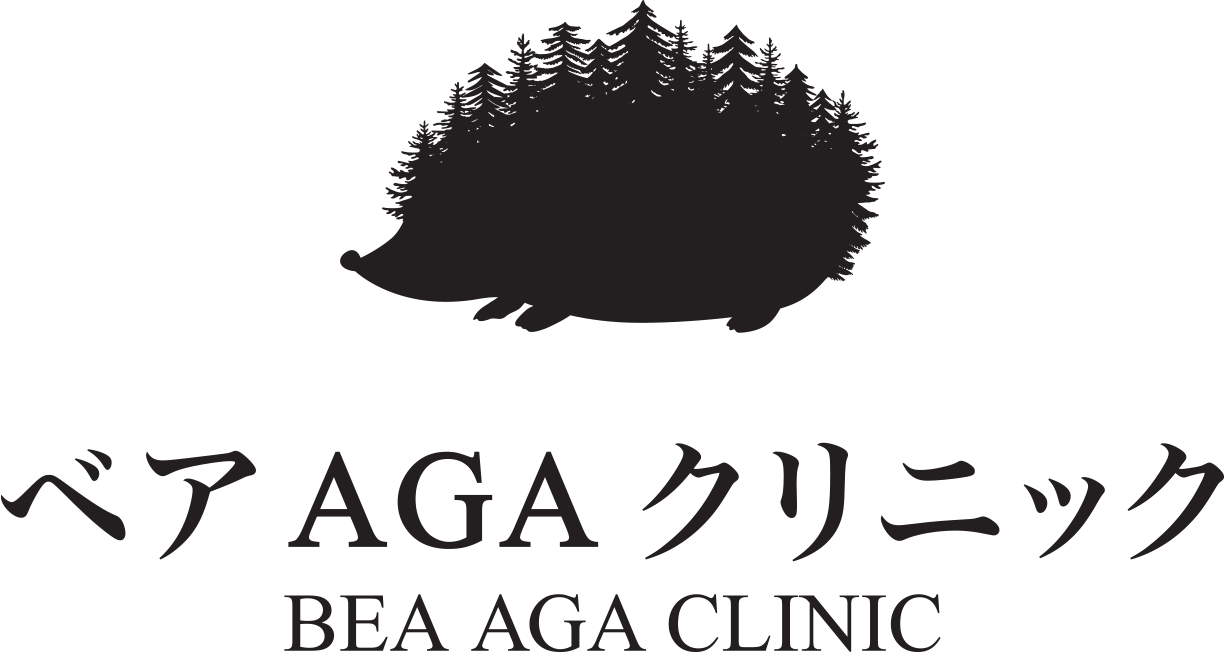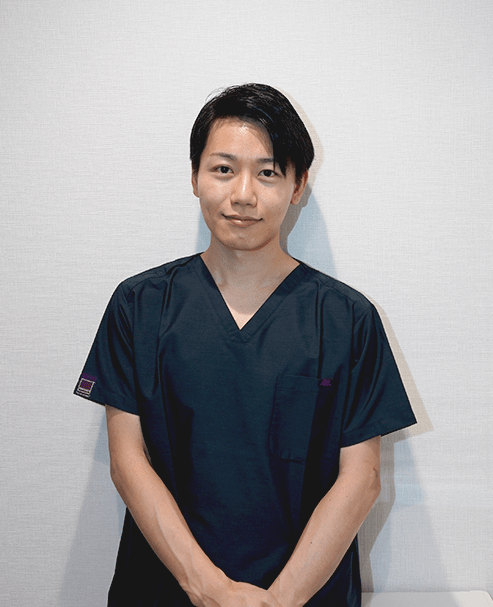最近、「急に髪の毛が抜ける」「枕に大量の抜け毛がある」といった症状に不安を感じていませんか?
髪の毛が異常に抜ける原因は、生活習慣の乱れやストレスだけでなく、女性特有の病気やホルモンバランスの変化、内臓の疾患など、さまざまな要因が複雑に絡んでいます。
中でも、FAGA(女性男性型脱毛症)や甲状腺疾患、膠原病などの病気は、症状に気づきにくく、気づいたときには症状が進行していることもあります。
本記事では「髪が抜ける病気」をキーワードに、女性の脱毛トラブルの原因や見分け方、必要な対処法までを医学的視点で詳しく解説します。
髪が抜けるのは病気のサイン?早期発見が大切

髪が抜けるという現象は、誰にでも起こり得る自然なことですが、「明らかに抜け毛の量が増えてきた」「髪を触るたびにごっそり抜ける」など、急激な変化を感じた場合には注意が必要です。特に、日常生活で明らかなストレスや体調不良がないにもかかわらず、短期間で大量に髪が抜けるようであれば、何らかの体内の異常や疾患の前触れである可能性が高まります。
毛髪の成長サイクルは「成長期」「退行期」「休止期」の3段階で構成されていますが、このサイクルは全身のホルモンバランスや免疫機能、栄養状態と密接に関係しています。つまり、体調の変化や内臓の不調が起こると、まずは目に見える変化として髪に現れることが多いのです。たとえば、内臓疾患やホルモン異常があると、成長期の髪が突然休止期へと移行し、短期間で一気に抜ける現象が起こることがあります。
また、「脱毛は皮膚や髪だけの問題」と思われがちですが、実際には全身性の疾患が関与しているケースも多く見られます。たとえば、自己免疫疾患では免疫システムが毛根を誤って攻撃することで脱毛が起こりますし、肝機能の低下や甲状腺の異常があれば、代謝に影響し毛髪の生成に必要な栄養が不足することで抜け毛が進行します。
さらに、女性の身体は月経周期や妊娠、閉経などによってホルモン変動が大きく、髪の毛の健康にも影響が出やすい傾向にあります。それゆえ、「いつものこと」と軽視してしまいがちですが、進行性の脱毛症の場合、初期対応を怠ると元に戻すのが困難になることもあるのです。
髪の変化は、身体が発する最初の異常のサインである場合があります。軽視せず、少しでも気になる症状があれば、皮膚科や専門のクリニックを早めに受診することで、病気の早期発見・早期治療につながります。
女性に多い「髪が抜ける病気」の代表例と特徴
女性の脱毛には、加齢や生活習慣の影響だけでなく、ホルモンの乱れや内臓疾患、自己免疫の異常といった医学的な要因が関わっていることがあります。特に女性はホルモンバランスが変化しやすく、20代後半から40代、そして閉経前後にかけてさまざまな病気が発症・進行しやすい時期でもあります。続いては、髪が抜ける原因となる代表的な病気を4つに分けて詳しく解説します。
① FAGA(女性男性型脱毛症)

FAGA(Female Androgenetic Alopecia)は、女性特有の進行性脱毛症であり、主に頭頂部から分け目を中心に徐々に薄毛が進行していくのが特徴です。男性のAGAのように前頭部や生え際が後退することは少なく、全体のボリュームが少なくなってきた、地肌が透けて見えるなどの自覚症状から始まります。
原因として最も注目されているのがDHT(ジヒドロテストステロン)という男性ホルモンの一種です。女性でも加齢や閉経などでエストロゲン(女性ホルモン)が減少すると、DHTの作用が優位になり、毛包がミニチュア化(小型化)していきます。これは髪の成長サイクルを短くし、太く長い髪が育たなくなる原因となります。
ベアAGAクリニック院長の見解では、「DHTが主因であり、エストロゲンの減少はその補助的な要因と考えられる」とされており、一般的な見解とも一致します。また、血液中のホルモン量ではなく、頭皮組織内でのDHT濃度が実際の症状に影響しているという説もあり、血液検査だけでは正確な診断が難しいという課題も存在します。
FAGAはゆっくりと進行するため、見逃されやすいですが、早期発見と医療機関での正確な診断が重要です。市販の育毛剤では改善が見られない場合、専門的な治療を受ける必要があります。
② 甲状腺機能異常(バセドウ病・橋本病)

甲状腺は首の前側にある小さな臓器ですが、体の代謝やエネルギー消費をコントロールする甲状腺ホルモンを分泌する重要な器官です。異常が生じると、髪の成長サイクルが乱れ、抜け毛が増えることがあります。代表的な疾患には、バセドウ病(甲状腺機能亢進症)と橋本病(甲状腺機能低下症)があります。
バセドウ病では、代謝が異常に活発になるため、体重減少や頻脈、手の震え、不眠などの症状が出るほか、髪も細く弱くなり、急激な脱毛が起こることがあります。一方、橋本病では代謝が低下するため、むくみ、寒がり、だるさなどに加え、髪がぱさつき、ゆっくりと抜けていく傾向が見られます。
特に女性は、出産後や更年期に甲状腺の病気を発症するリスクが高く、その際に脱毛症状が強く出ることもあります。甲状腺ホルモンは毛根細胞の活動を支えるエネルギー源の一つであり、ホルモン量が過剰でも不足しても脱毛が起こり得るという点が非常に重要です。
脱毛の背景に甲状腺の異常がある場合、皮膚科ではなく内分泌科や総合内科での診断と治療が必要です。単なる美容の問題ではなく、全身の健康状態の警告サインとしての脱毛であることを認識することが大切です。
③ 膠原病(SLEなど)

膠原病とは、免疫システムが自分自身の細胞や組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の総称で、特に女性に多く見られる疾患です。代表的なものに全身性エリテマトーデス(SLE)があり、若年女性(10代後半〜30代前半)に発症するケースも少なくありません。
SLEでは、皮膚・関節・腎臓など複数の臓器が同時に炎症を起こし、円形脱毛や全体的なびまん性脱毛(広がるように抜ける)といった脱毛症状を引き起こすことがあり、単なるホルモンバランスの乱れではなく、免疫異常によって毛根がダメージを受けることが原因です。
また、膠原病ではステロイドなどの免疫抑制剤を長期服用するケースもあり、これがさらに脱毛を悪化させる可能性もあります。つまり、病気そのものと薬の副作用の両方が髪に影響するという点で、一般的な脱毛症とは異なる注意が必要です。
膠原病による脱毛は、美容面の問題にとどまらず、全身の炎症の一部として現れている重要な症状の一つであるため、必ず専門医の診断と長期的な管理が必要となります。
④ 内臓の病気と髪の関係

髪の健康は、外見からは見えない体内の臓器の健康状態を反映するバロメーターでもあります。肝臓、腎臓、消化器官といった主要な臓器にトラブルがあると、栄養の吸収・代謝・排出といった生命維持機能が低下し、結果として髪に栄養が届かなくなります。
たとえば、慢性的な肝機能障害(脂肪肝や肝炎など)では、髪の材料となるタンパク質の代謝に支障が出ます。また、腎臓疾患では体内の老廃物が適切に排出されず、血流や代謝に悪影響を及ぼし、毛根の働きを妨げることもあり、糖尿病や鉄欠乏性貧血なども、抜け毛や髪の質の低下を引き起こす要因になります。
| 内臓疾患 | 脱毛との関係 |
|---|---|
| 肝疾患(脂肪肝、肝炎) | タンパク質代謝障害による毛髪の材料不足 |
| 腎疾患 | 老廃物の蓄積と血流障害による毛母細胞の活動低下 |
| 糖尿病 | 血流悪化による毛包の栄養障害 |
| 貧血(鉄欠乏) | ヘモグロビン不足による酸素供給低下と脱毛 |
年齢別に見る脱毛の特徴と注意点

髪の毛の健康状態や抜け方には、年代ごとに異なる特徴やリスク要因があります。
思春期にはホルモンバランスの急変が、30代以降では加齢による女性ホルモンの変化が、さらに50代以降には血行不良や代謝の低下が関係することが多く、それぞれの年代特有の背景が脱毛の引き金となるのです。
また、年齢が進むほど脱毛が「一時的なトラブル」ではなく、慢性的・進行性の病態へと移行するリスクも高まります。
このため、年齢に応じた正しい理解と、必要に応じた医療機関での相談が重要となります。
思春期・中学生に多い「円形脱毛症」
思春期の子どもや中学生の脱毛症状として最も多く見られるのが「円形脱毛症」です。
円形脱毛症は自己免疫疾患の一種であり、免疫機能が誤って自分の毛根を攻撃してしまうことが原因と考えられています。
特に中学生のように思春期を迎えたばかりの時期は、ホルモンバランスが急激に変動し、加えて学校生活や人間関係のストレスも重なりやすい環境です。こうした心理的・身体的なストレスが引き金となって、突然髪の一部が円形に抜け落ちることがあります。
早期に皮膚科や専門クリニックで対応すれば、自然治癒や再発予防が可能なケースも多いため、保護者の早期対応が非常に大切です。放置すると症状が進行し、全頭型や汎発型へ移行するリスクもあります。
30代以降の女性に多いFAGA
30代以降の女性に増えてくるのが、女性男性型脱毛症(FAGA)です。
30代では、仕事・出産・育児・家庭など多方面でのストレスが重なりやすく、それがホルモンバランスの乱れや自律神経の不調につながることも少なくありません。
さらに、エストロゲン(女性ホルモン)の分泌が緩やかに減少し始めるため、相対的にジヒドロテストステロン(DHT)の影響を受けやすくなるのが特徴です。
FAGAは、髪が一気に抜け落ちるというよりも、「気づいたら分け目が目立つ」「髪が細くなってきた」というように、徐々に進行する点が特徴で、初期段階では気づきにくいのも厄介な点です。
このため、「疲れやすいから」「年齢のせいかも」と見過ごさず、進行性の症状である可能性を疑い、専門医に相談することが重要です。
50代以降に増える「慢性脱毛」
50代以降になると、多くの女性が抱える脱毛の悩みは「慢性脱毛」と呼ばれる進行性の脱毛状態です。
この時期は閉経を迎え、女性ホルモン(特にエストロゲン)が大幅に減少することで、頭皮の皮脂バランスが崩れたり、血流が悪くなったりするなど、頭皮環境が大きく変化します。
さらに、年齢に伴う代謝の低下や栄養吸収率の低下により、髪の成長に必要な栄養素が毛根に十分に届かなくなることも原因です。
症状としては、「抜け毛が増える」というよりも、「髪の本数が減っていき、地肌が透けて見える」「髪のハリ・コシが失われる」といった形で現れます。
この年代の慢性脱毛はFAGAと合併することも多いため、加齢による自然現象と片付けず、医師の診断を受けることが、状態の把握と適切な治療の第一歩となります。
「急に髪の毛が抜ける」症状を感じたときのチェックポイント

髪の毛は通常、1日50~100本程度が自然に抜けており、「ヘアサイクル(毛周期)」と呼ばれる自然なサイクルの一部です。しかし、明らかに抜け毛の量が増えたと感じたり、ある日を境にごっそり抜けるようになった場合、それは身体からの異常サインの可能性があります。
たとえば、朝起きたときに枕元に大量の抜け毛があったり、シャンプーやブラッシングのたびに手やブラシに抜け毛が大量についているといった場合には、急性の脱毛症やホルモンバランスの急変、または免疫系の異常などの背景疾患が隠れている可能性があります。一見、些細に思えるかもしれませんが、放置することで抜け毛が進行し、回復が難しくなるケースもあるため注意が必要です。
特に女性の場合、ストレスや睡眠不足といった一時的な生活習慣の乱れによっても抜け毛が増えることはありますが、数日〜数週間にわたって抜け毛が止まらない場合は、自己判断せず専門の医療機関を受診することを強くおすすめします。脱毛は、皮膚科や脱毛症専門のクリニックで頭皮の状態や毛根の成長段階を確認することで、比較的早期に原因の特定が可能です。
加えて、「いつから抜け毛が気になり始めたのか」「どのような部位から抜けているのか」「家族に同じような症状があるか」など、自分自身の症状や変化を具体的に記録しておくことも、正確な診断を受けるうえで重要です。 例えば、円形脱毛症のように明確な境界を持つ脱毛パターンなのか、FAGAのように全体が薄くなってきているのかといった違いを医師に伝えることで、診断精度が高まります。
男性にも要注意!髪が異常に抜ける原因

「髪が抜ける病気=女性の悩み」と思われがちですが、実際には男性も深刻な脱毛症に悩むケースが少なくありません。特に30代以降の男性で、「シャンプーのたびにごっそり抜ける」「頭皮が透けて見える」といった症状に気づいたとき、それは進行性の脱毛症が始まっているサインかもしれません。
抜け毛は加齢とともに自然に起こる現象の一つですが、「異常に多い抜け毛」や「短期間で進行する薄毛」は明らかに通常の生理現象とは異なります。こうした症状が見られる場合、内的な疾患やホルモンの乱れ、または頭皮環境の悪化が関与している可能性があります。
また、女性と同様に、男性もストレスや食生活の影響を強く受けることがわかっており、単なる加齢だけでは説明のつかない進行性の脱毛が起こることもあります。自覚症状があるにもかかわらず放置すると、脱毛部位が広がり、治療の選択肢や効果に大きな影響を与えるリスクが高まるため、早めの対策が非常に重要です。
AGA(男性型脱毛症)

AGA(Androgenetic Alopecia)は、男性の脱毛症の中で最も多く見られる進行性の病気です。20代後半から30代にかけて発症するケースが多く、特に前頭部の生え際や頭頂部から徐々に薄毛が進行していく特徴があります。
AGAの主な原因は、男性ホルモンの一種であるDHT(ジヒドロテストステロン)の作用です。DHTは毛根にある「アンドロゲン受容体」と結合することで、毛母細胞の分裂を阻害し、髪の成長サイクルを短縮させてしまうのです。その結果、髪は十分に太く長く育たないまま抜け落ち、次第に髪の密度が低下していきます。
さらに重要なのは、AGAは「自己免疫疾患」や「皮膚炎」のように目立った炎症や痛みが伴わないため、発症に気づくのが遅れやすいという点です。抜け毛の量や髪質の変化、家族に薄毛の方がいるかどうかといった点も重要な判断材料となります。
また、市販の育毛剤だけでは進行を止められないことが多いため、AGAの兆候がある場合は、医師の診断を受け、内服薬(フィナス
生活習慣やストレスの影響もある

AGAのようなホルモン性の脱毛症とは異なり、生活習慣やストレスによる抜け毛は一見目立たない形で進行するため、見過ごされやすいのが特徴です。しかし、慢性的な睡眠不足や偏った食生活、運動不足などが続くことで、頭皮環境が悪化し、抜け毛が加速する可能性は十分にあります。
特にストレスによって分泌されるコルチゾールというホルモンは、毛包の成長期を阻害し、休止期を早めてしまうことが分かっています。その結果、髪が抜けるだけでなく、新しい毛の発育も抑えられてしまい、ボリュームのない状態が長く続くのです。
さらに、現代の男性は、デスクワークやリモートワークの増加により、血行不良による頭皮への栄養不足に陥りやすい傾向にあります。頭皮の血流が滞ると、髪に必要な酸素や栄養素が届かず、結果として健康な髪を育てる土台が失われてしまうのです。
このようなタイプの脱毛は、ホルモン治療だけでは改善されにくいため、生活習慣の見直しやストレスマネジメントといった根本的なアプローチが必要不可欠です。日常的に行うセルフケアの質が、将来の髪の量を左右する可能性すらあるといえるでしょう。
FAGAとAGAの違いとは?

FAGAとAGAは、どちらも「脱毛症」という共通点がありますが、発症メカニズムや進行パターン、治療法には大きな違いがあります。とくにFAGAは、「女性型脱毛症」と訳されることもあり、見た目の症状や原因がAGAとは異なる点が多く、性別によるホルモン環境の違いを理解することが治療の第一歩になります。
まずAGAは、主にテストステロンがDHT(ジヒドロテストステロン)に変換されることで毛根に作用し、毛周期が乱れて脱毛が進行する病気です。とくにM字や頭頂部の生え際が徐々に後退する「局所的な薄毛」が特徴であり、進行も比較的分かりやすいのが特徴です。男性ホルモンの影響を強く受けるため、遺伝的要因が関係することも多く、発症年齢も10代後半〜20代前半と早い傾向があります。
一方でFAGAは、女性特有のホルモン環境の変化に加えて、DHTの影響も受けながら複合的に進行するのが大きな違いです。とくに30代以降、出産や更年期を迎えるタイミングでエストロゲンが減少し、DHTとのホルモンバランスが崩れることで症状が現れるケースが多いとされています。
またFAGAは、頭部全体の髪の密度が均一に減っていく「びまん性脱毛」が主症状で、M字や頭頂部といった特定部位が目立って薄くなることは少ないという特徴があります。そのため、「なんとなく髪が細くなった」「ボリュームが出ない」といった変化に本人が気づきにくく、治療が遅れやすいという問題もあります。
FAGAとAGAの違いを比較
| 項目 | AGA(男性型脱毛症) | FAGA(女性男性型脱毛症) |
|---|---|---|
| 主な原因 | DHT(ジヒドロテストステロン) | DHT+エストロゲンの低下など複合的要因 |
| 発症年齢 | 10代後半〜40代以降 | 30代〜60代(更年期含む) |
| 症状の範囲 | M字、生え際、頭頂部の局所的な薄毛 | 頭部全体のびまん性脱毛 |
| 見た目の特徴 | はっきりした薄毛部位 | 全体的なボリュームダウン |
| 自覚しやすさ | 見た目に明らかで自覚しやすい | 気づきにくく、進行しやすい |
| 治療の選択肢 | フィナステリド、ミノキシジルなど | スピロノラクトン、ミノキシジルなど |
またAGAの治療が比較的確立されている一方で、FAGAは原因が複雑であるため、治療には個別対応が必要です。例えば、ミノキシジルだけでなく、女性ホルモンのバランス調整や栄養療法、漢方、生活指導などを組み合わせた総合的なアプローチが求められます。
FAGAとAGAは「ホルモンによる脱毛症」という共通点を持ちながらも、仕組みや治療方針は大きく異なります。女性の薄毛治療においては、FAGAの理解と正確な診断が不可欠であり、男性用の治療薬をそのまま使用するのは避けるべきです。
病気が原因の抜け毛は、治療で改善できる

髪の毛が抜ける原因が、単なる加齢や生活習慣ではなく「病気」によるものである場合、病気自体を適切に治療することで、脱毛の改善が十分に期待できます。特に自己免疫疾患や内分泌異常、重度の栄養障害が関与しているケースでは、髪の症状はあくまで“全身の異常の一部”として現れているに過ぎません。
たとえば、鉄欠乏性貧血やビタミンB群の不足が原因となっている場合は、医師の指導のもとでサプリメントや点滴治療を行うことで、比較的短期間での改善が見られることもあります。栄養関連の脱毛は、特にダイエットや偏食傾向の強い若年層の女性に多く見られ、病気として自覚されにくい点が課題です。
また、糖尿病や腎機能障害などの慢性疾患に伴う脱毛では、血行障害や毛母細胞への栄養供給不足が原因になっているケースもあります。これらは、病気の進行によって毛根の機能が低下している状態なので、血糖値のコントロールや腎機能の改善を優先しつつ、毛髪再生治療を併用することが有効です。
脱毛の根本的な解決には「髪だけを見る」のではなく、「全身の健康状態を包括的に評価する」ことが不可欠です。症状が髪に現れていても、その背後にある内科的疾患やホルモン異常にアプローチしなければ、いくら育毛剤やシャンプーを使っても効果が出にくいことは明白です。まずは医療機関で正しい診断を受け、必要に応じて専門クリニックと連携する形で、治療を進めることが大切です。
まとめ:髪が抜ける病気は、早めの対応がカギ!薄毛にお悩みの方はベアAGAクリニックへ

髪が抜ける原因には、FAGAや甲状腺の異常、内臓疾患など、さまざまな病気が関与している可能性があります。症状が進行してからでは回復に時間がかかるため、早期の発見と対策が重要です。「もしかして…」と感じたときこそ、専門の医療機関での診断が必要です。髪の変化に気づいた今が、対策を始める絶好のタイミングです。
薄毛のお悩みは、専門の医師が在籍するベアAGAクリニックにお気軽にご相談ください。まずは無料カウンセリングであなたの髪の状態をチェックしてみましょう。